



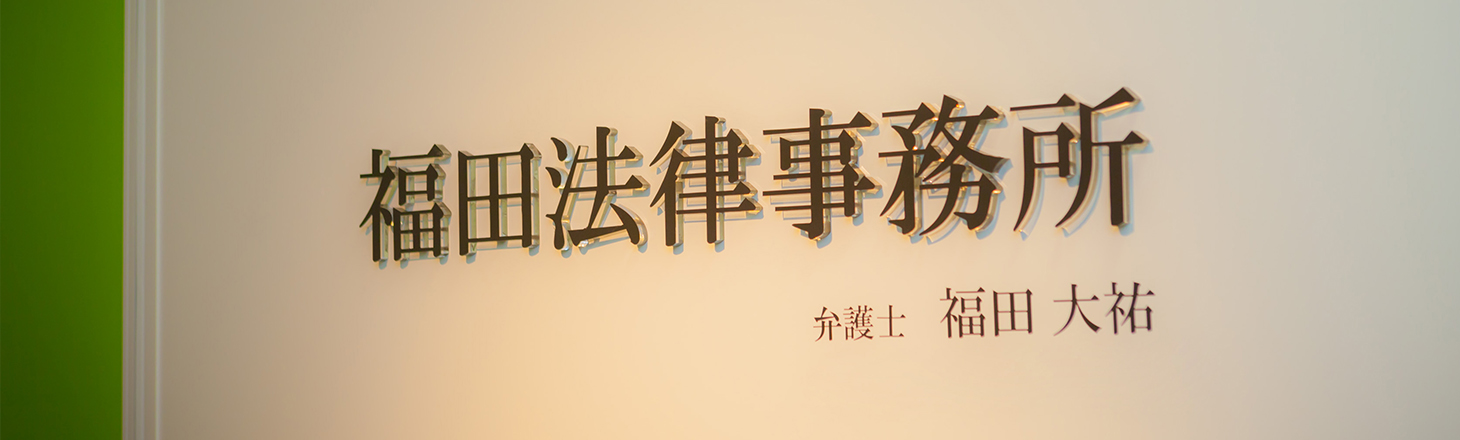
超高齢化社会の進行に伴い、老後の資産管理に不安を覚える人が増えています。認知症などの病気が原因で判断力が低下してしまうと、自分で財産を適切に管理するのは困難です。さらに、裁判所で後見開始の審判などを受けた場合には、資産を自由に動かすことすらできなくなってしまいます。
こうした事態の解決策として、今注目されているのが「家族信託」といわれる手法です。
Q:私は現在70代。今はまだ元気ですが、将来もし認知症になったらと思うと心配です。そろそろ体力の衰えも気になりますし、もしものときに備えて近くに住む娘に自分の財産を管理してほしいと思っています。最近、家族信託というものがあることを知ったのですが、具体的に何をすればいいですか?
家族信託とは、信頼できる家族や親戚に自分の財産を託し、運用や管理を任せる制度です。本人が望むような形での財産管理ができる、元気なうちに家族に自分の財産を継承できる、といったメリットがあります。
上記の事例でも、家族信託を利用すれば、本人の判断力が低下する前に財産の管理を適切な人材に任せられます。
この段落では、家族信託の仕組みについて簡単に説明します。
家族信託の基礎となっているのは、信託契約といわれる契約です。この信託契約を、財産を託したい人(委託者)と財産を託されたい人(受託者)の間で結ぶことで、信託が始まります。
信託契約を結ぶと財産の名義は委託者から受託者に移りますが、受託者ができるのは財産の管理や運用などに限られます。財産を売却して得た代金や運用益といった利益を受け取る権利はありません。
財産から利益を受け取る権利は受託者ではなく、受益者といわれる人にあります。この受益者は委託者と同一人物でも、また全く違う別の人物でも構いません。
家族信託を上手に利用できれば、大切な財産を柔軟に活用しつつ、万が一の事態にも備えられます。さらに、自分以外の誰かを受益者とすれば、財産を親しい家族に残すことも可能です。そのため、家族信託は生前相続対策としても活用されています。
家族信託を活用するメリットが大きい場面としては、次のようなケースが挙げられます。
他にも、家族信託が役立つ場面はまだまだあります。もし自分の老後や相続のことが気になりだしたら、一度弁護士に相談してみてはどうでしょうか。家族信託を含む相続関係の相談の他、信託契約を結ぶときの契約書の書き方などについてもアドバイスがもらえます。法律のプロならではのきめ細やかなサポートで、将来に備えましょう。