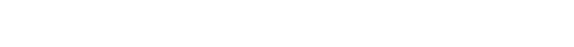
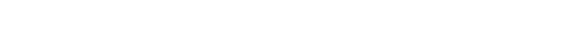
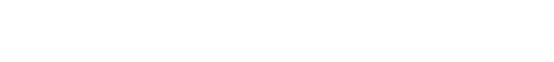


相談者は兄と2人兄弟で,母,兄が既に亡くなっているところに今回父親が亡くなり相続が発生しました。
代襲相続人である兄の子らは,遺産すべてを兄の子らに相続させる旨の父親の遺言があることを理由に,遺産のほとんどを占める父親の自宅に自分たちの母(兄の妻)を生涯住まわせることを主張しました。相談者は,父親の血を引かない兄の妻に実家を奪われることに心理的に抵抗があり,相続の話し合いはまとまりませんでした。そこで,相談者が遺留分減殺請求について相談に来られました。
遺留分減殺請求訴訟を提起したところ,交渉の段階では話に出なかった兄の父親に対する貸金の存在を主張し始めました。そして,兄の貸金に対する代物弁済として,父親が兄の妻に自宅の所有権を譲渡したので,自宅は遺留分減殺の対象とならないと主張するようになりました。
こちらは,代物弁済の証拠となる書証に偽造の疑いがあること,当時兄が父親に貸すだけの資金を有していなかったことを様々な証拠から立証し,兄から父親への貸し付けと父親の代物弁済は存在しなかったと主張しました。
結局,一審ではこちらの主張が認められ,控訴審で和解し終了しました。
相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。
同じく相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。
本件は少し複雑な家系における相談でした。相談者は被相続人の先妻の子で,被相続人の後妻は認知症が進んでおり,被相続人と後妻との間には,相談者より30歳以上も若い養子がいました。
被相続人は,遺産をすべて後妻に相続させる旨の公正証書遺言を亡くなる5年前に作成していましたが,遺言執行者として,養子の実父が指定されていました。また,被相続人と養子との間の養子縁組は,遺言作成と同時に行われていました。
相談者は,遺言作成と養子縁組に至る事情に納得がいかず,遺留分減殺請求をすることにしました。
被相続人の相続人は長男、次男、長女の3人の子で、相続人間に交渉がなく、当初は次男と長女が申立人、長男を相手方として遺産分割調停を申し立てました。
ところがその遺産分割調停の第1回期日前に、長男側から被相続人の遺言が出てきました。
遺言の内容は、長男に遺産のすべてを相続させるとの内容でした。
そこで、次男と長女が、長男を相手に遺留分減殺(侵害額)請求訴訟を提起しました。
父親が亡くなって遺産を確認したところ、数年前には確かに4000万円を超える預金を有していたはずなのに、100万円しか残っていませんでした。
亡くなる10年前から父親と同居していた相談者の兄弟が、認知症になった父の預金を引き出して使ったことが強く疑われる事案でした。
また、遺言があり、父と同居していた相談者の兄弟にすべて相続させるという内容でした。
相談者は遺留分減殺請求をしましたが、争点は生前に預金口座から引き出された金銭の使途でした。
詳しく見る >
有効な遺言が存在する以上,自宅の所有権自体をこちらで取得することは困難でしたので,遺留分減殺請求により,遺留分減殺額相当の和解金を受け取ることで終了になりました。当初計算していた金額ほぼ変わらない価格弁償を受けることができたので,相談者にも納得いただけ和解に至ることができました。