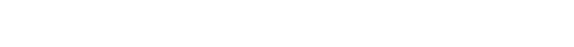
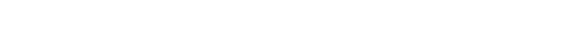
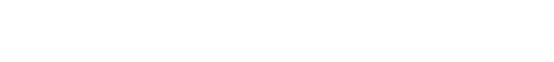


遺留分とは、遺言に従うと相続財産がない法定相続人にも最低限保障されている、遺産の取り分のようなものです。
たとえば、妻と子ども2人が法定相続人となっているときに、遺言で妻だけに相続させる旨が記載されていたとしても、他の法定相続人である子ども2人は遺留分を主張して相続財産の一部を受け取ることができるのです。
もし、他の法定相続人による遺留分の主張を許さず妻だけに遺産を相続させたいと思ったら、子ども2人には遺留分を主張させないようにする必要があります。
では、遺言で遺留分を奪うことはできるでしょうか?
残念ながら(?)、遺言で遺留分を奪うことはできません。
遺言者は、原則として自分の財産の処分を遺言で自由に決めることができます(遺言自由の原則)。なぜなら、生きている間に自分の財産をどう処分するかは完全に自由であり、この自由を死後にも及ぼすのが遺言だからです。
しかしながら、この原則を貫くと相続できなかった相続人は、生活の糧を突然奪われることにもなりかねません。そこで、最低限の取り分を保障するため、遺留分の範囲で遺言自由の原則を制限しているのです。
遺言で遺留分を奪うことはできませんが、本人が自発的にする限りにおいて、家庭裁判所の許可を得て事前に遺留分を放棄させることは可能です。
相続放棄とは異なり、遺留分の放棄は相続の開始前からすることができます。
実際の運用は各家庭裁判所によって若干の違いはありますが、遺留分の放棄の申立てがあった場合、家庭裁判所は本人に対して照会書を送り、遺留分の放棄が真意によるものかどうか確認してから許可を出しています。
これはおそらく、遺留分の放棄が相続開始前にできることから、本人から圧力がかかり、本意でない遺留分放棄を強制されていないかを確認しているのだと思われます。
ですので、遺留分の放棄は本人が納得していない限りできないものと考えるべきです。もし遺留分の放棄をさせるのであれば、それに代わる何らかの代償を用意する必要があるでしょう。
また、相続人を廃除する方法も考えられます。
民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。民法第893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
相続人を廃除すれば、排除された人は相続人でなくなるため、遺留分も主張できなくなります。
相続人を廃除する方法は、家庭裁判所に相続人廃除の申立てをするか、遺言で相続人の廃除をする
ことでできます。 どちらの場合も、廃除するかどうかの最終判断は家庭裁判所が行います。
廃除の要件は①被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱を加えたこと、②その他の著しい非行があったこと、ですので、どちらかの事情がなければ家庭裁判所は廃除を認めません。
めったにあることではありませんし、あってはならないことですが、相続人に欠格原因があれば相続できなくなります(民法第891条)。
・相続開始後に他の相続人を強迫した
・不正に利益を得ようと他の相続人を殺害した
・遺言書を偽造した
相続人が上記のような行動をとれば、家庭裁判所へ申立てをしなくてもその相続人は相続人としての資格を失うことになります。
・生前に相続人廃除の申立てを行い、家庭裁判所が廃除を認めた
・相続開始後に相続人が悪質な行為を行い、相続権を失った
これらの事実によって相続人の相続権がなくなったとしても、その相続人に子どもがいれば、代襲相続人として相続権が継承されます。 代襲相続という制度がある以上、完全に相続権を奪うことはできないのです。
これに対し、遺留分の生前放棄を家庭裁判所へ申立てをしたものの、相続開始までに遺留分放棄した推定相続人が亡くなり、相続開始時に代襲相続になっている場合は、遺留分の放棄は引き続き効力を有すると考えられています。
もし、これから作成する遺言の遺留分を放棄させたいが、どうしてよいかわからず困っている場合には、まずは一度、遺産問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
このコラムの監修者

福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。
2019年7月に相続法は1980年以来、約40年ぶりに大きく見直されました。 改正の背景は、国民の平均寿命が延びて高齢化社会が発展するなど社会経済が大きく変化したことから、その変化に対応するためです。 相続法改正に伴い、相続人が最低限受け取れる財産範囲を示す遺留分制度も見直されています。 具体的に今までの遺留分制度と何が変わったのでしょうか? 今回は...
詳しく見るはじめに海外のニュースで、「亡くなった大富豪からペットに〇億円の遺産」などといったニュースを聞いたことがありませんか。ペットの相続権を法律で認めている国は珍しくありません。では、日本でペットに全財産を相続させたい場合、どのようにすればいいでしょうか。 ペットは財産を相続できない日本においてペットは「所有物」です。人間にしか相続を認めていない日本では、残念な...
詳しく見る