
遺留分侵害額請求権とは?(2)~請求の方法と流れ
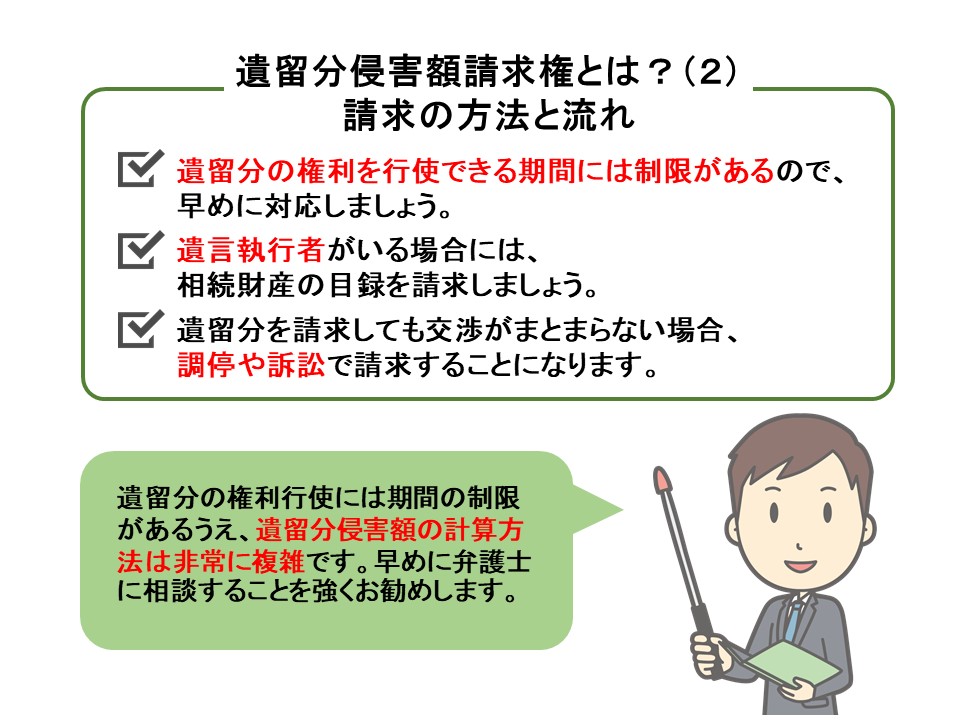
相続において、最低保証額のような性質を持つ「遺留分」。この遺留分は「遺留分侵害額請求権」に基づいて請求が可能です。
前回は、遺留分を請求できる場合や、人について解説しました。
今回は引き続き、請求の方法と流れについてみていきましょう。
目次
遺留分侵害額請求の期限
前回説明したとおり、遺留分侵害額請求をするかどうかは、遺留分権利者の意思に委ねられています。
遺留分侵害額請求を受ける側からすれば、いつ遺留分の請求を受けるか分からないようではうかつに遺産を処分することもできなくなり困ります。
そこで民法は、遺留分侵害額請求ができる期間を制限しています。
第1048条 (遺留分侵害額請求権の期間の制限)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
つまり遺留分侵害額の請求は、以下の両方を満たすうちにしかできません。
- ①相続開始(=被相続人が亡くなったこと)と遺留分の侵害があったことの両方を知ったときから1年以内
- ②相続開始から10年以内
このように遺留分侵害額請求は、いつでも可能なわけではありません。
まずは期限内であることを確認し、できるだけ早めに対応することが大切です。
次は、遺留分侵害額請求の具体的な順序・方法について解説します。
遺留分侵害額請求の意思表示(内容証明郵便)
先ほど説明した通り、遺留分侵害額請求は期限内にしなければ権利を失います。
したがってまずは、遺留分侵害額請求をする、という意思を請求の相手に伝えるのが最初にすべきことです。
これは口頭や普通の手紙で伝えるのではなく、内容証明郵便で送付します。
というのも、間違いなく期限内に遺留分の請求をしたということを、後日争われないように証拠化しておくためです。
この内容証明郵便の送付を先ほどの1年あるいは10年の期限内にしておけば、あとは期限の問題はなくなります。
なお、この段階で伝える必要があるのは遺留分侵害額請求をする意思がある、ということだけです。具体的な請求金額は後日で構いません。
もし誰が遺留分侵害額請求の相手になるかまだ分からない場合は、相続人と受贈者全員に請求するとよいでしょう。
相続財産調査
遺留分を計算するにあたっては、相続の対象となる財産がどこに、どのくらい、どういった形で存在するのかを調査します。
遺産目録を作成する作業と考えてもらえばよいでしょう。
相続財産がすべて判明している場合はよいですが、遺留分を請求する側が相続財産の詳細を把握していることは、通常は少ないと思います。
ですので遺留分請求の相手方となる相続人、あるいは一番相続財産を把握している相続人に、遺産の内容を照会します。
遺言執行者がいる場合は、遺言執行者に財産目録の交付を要求します。
これは1011条で、遺言執行者の義務になっています。
第1011条(相続財産の目録の作成)
1 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
もし、遺言執行者もなく、他の相続人の協力も得られない場合、自分で遺産を調査しなければなりません。
遺留分侵害額の計算
相続財産が判明したら、いよいよ遺留分侵害額の具体的計算を行っていきます。ここから先は、少し専門的な説明になります。
遺留分算定の基礎となる財産
まずは、遺留分侵害額を計算するベースとなる財産を確定させます。
具体的には、相続開始時の財産(遺産)に、生前贈与を行った財産を加え、そこから債務を差し引いて計算します。
これは民法第1043条に規定があります。
第1043条 (遺留分を算定するために財産の価額)
1 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
具体的遺留分
確定した遺留分算定の基礎となる財産をもとに、遺留分を計算します。
遺留分の計算は、「遺留分の基礎となる財産×遺留分割合×法定相続分」で求められます。
遺留分割合は、前回説明した通り、直系尊属(父母・祖父母)のみが相続人である場合を除き、2分の1です。
具体的な計算例
被相続人Aさんが亡くなったとき預金5000万が残っており、亡くなる半年前に2000万円の生前贈与が確認された。
また、債務が1500万円あった。
相続人は妻と子ども3人のみである。
- ①遺留分の基礎となる財産=預金5000万+生前贈与2000万-債務1500万=5500万円
- ②妻と子供の遺留分合計額=5500万円×2分の1(遺留分割合)=2750万円
- ③妻の遺留分=2750万円×2分の1(法定相続分)=1375万円
- ④子どもの遺留分(1人分)=2750万円×6分の1(法定相続分)=約458万円
具体的金額の請求交渉
遺留分侵害額が判明したら、まずは侵害している相手に請求します。
平成30年の相続法改正により、遺留分侵害額請求は金銭の支払を請求することができる権利となっています(それ以前は、金銭の支払ではなく例えば遺産である土地の名義の一部を遺留分権利者に移転するのを原則としていました)。
相手が遺留分侵害している分の金銭を支払う姿勢を見せたら、直接交渉に入ります。
交渉の結果、無事合意に達したときは念のため合意書を作成しておきましょう。
相続税の課税対象となる相続の場合には、この遺留分侵害額請求の合意書において相続税の申告の修正の有無についても規定しておきましょう。
というのも、相続税を申告した後で遺留分侵害額を受けた相続人は、相続税の更正請求を行えば相続税の還付を受けることができます。
他方、遺留分侵害額請求によって金銭を受け取った相続人は、相続税の(修正)申告を行う必要があるからです。
裁判所の調停や訴訟で遺留分侵害額を請求する
遺留分を侵害している相手と直接交渉してもうまくいかなかったり、無視されたりする場合は、裁判所の手続を利用します。
裁判所を通じた遺留分侵害額請求の手続は、調停による場合と訴訟による場合の2通りがあります。
家事事件手続法では、遺留分侵害額請求はまず調停を提起し、そこで調停成立しなかった場合に訴訟を提起するよう求めています(調停前置)。
しかしこれには例外があり、調停で話し合っても合意できる見込みがない場合には最初から訴訟を提起しても認められる場合が割とあります。
遺留分侵害額請求調停は時間がかかりますが、それでも最終的に調停が成立しなければまた一から訴訟を提起しなければなりません。
合意の見込みがなければ、最初から訴訟を提起することも念頭に置く方がよいでしょう。
遺留分侵害額請求における争点
財産の評価額
遺留分算定の基礎となる財産は、相続財産調査で判明した財産の金額がベースとなります。
この財産が預金だけであれば、預金残高の合計そのままですから問題はありません。
しかし、たとえば自宅不動産が含まれるのであれば、その不動産の金額は固定資産税評価額なのか、相続税の申告評価額(路線価)なのか、それとも不動産業者の査定額または不動産鑑定士の鑑定額なのか、いろいろ考えられるところです。
また被相続人が会社のオーナーであればその所有する株式が遺産になりますが、これは株価がつかない非上場株式ですから、これを1株いくらで評価するかも、難しい問題です。
これらには決まった正解がなく、ゆえに遺留分侵害額請求において、しばしば争われる争点となります。
特別受益の持戻し
先ほど預金は預金残高がそのまま遺留分算定の基礎財産となるといいましたが、相続開始前に相続人の誰かが引き出している場合には、その引き出した金額を遺留分算定の基礎財産に反映させる必要があります(1042条~1044条)。
したがって、相続開始時の預金残高を確認するだけでなく、取引明細(取引履歴)を確認して生前の引き出しを確認しなければならない場合があります。
そして、生前に本人が引き出したと思われない疑わしい出金がある場合には、これが遺留分侵害額を決めるにあたっての争点となることがよくあります。
調停や訴訟を見越した相談を
今回紹介したように、遺留分侵害額請求には様々な書類の準備が必要なだけではなく、複雑な計算が必要になります。
また実際の請求にあたっても、直接交渉で解決できれば良いのですが、一度受け取った財産を素直に返還する方ばかりとは限らず紛争に発展するケースも少なくありません。
さらに、調停や訴訟には多くの書類が必要で、書類の作成だけで時間がかかってしまいます。
遺留分侵害額請求には期限がありますから、できるだけ効率的に手続きを進めたいところです。
もし話し合いで決着がつかず、調停や訴訟に発展しそうならば、相続に強い弁護士の手を借りるべきでしょう。
このコラムの監修者

-
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。








