
公正証書による遺言のメリットとデメリット
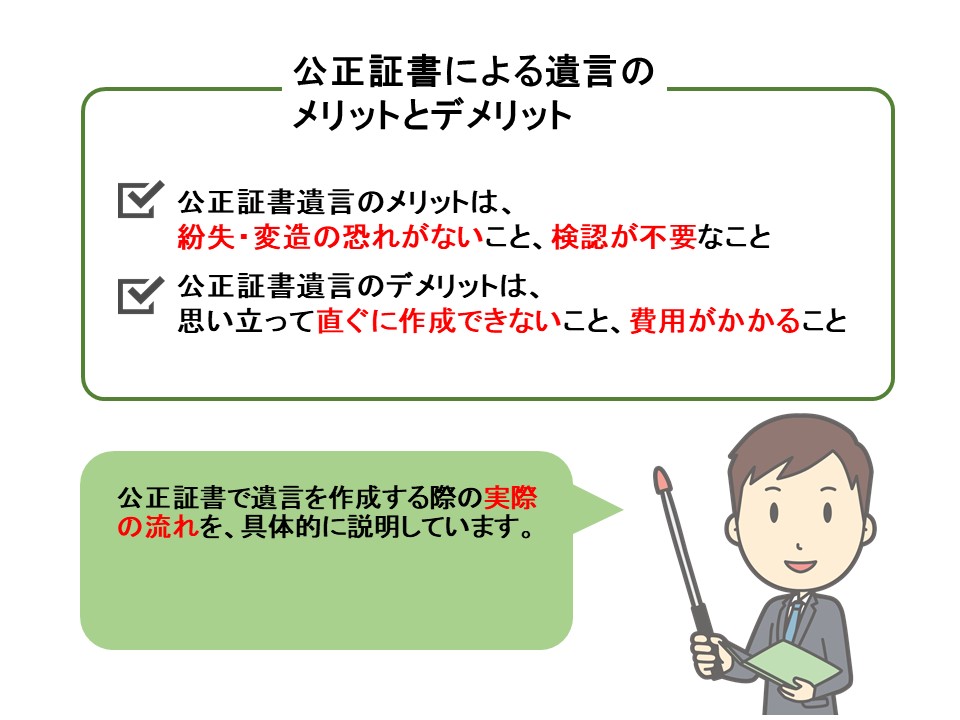
目次
1 公正証書とは
公正証書とは、法務省から任命された法律のプロである公証人が作成する公文書です。
公正証書は、公証人という資格者が作成する点で、信用力がある文書として扱われますので、公正証書は様々な場面で作成されることがあります。
遺言も、この公正証書ですることができます。
では、公正証書で遺言をすることに、どんなメリットがあるのでしょうか。
以下に公正証書遺言の詳細を見ていきましょう。
2 公正証書遺言を作成するときの手続の流れ
①原案の作成
遺言しようとする者が遺言の内容を考えて、原案を作成します。
公証人は、せっかく作成する遺言が無効になったり、解釈に疑義が生じたりしないよう形式面から遺言内容のアドバイスはしてくれますが、遺言者の状況と希望からみて当該遺言内容が適切かどうかまではチェックしないことが一般的です。
もしその点に不安があれば、弁護士に相談しましょう。
②公証役場の予約
公証役場に連絡して、原案を伝えて内容を確認してもらいます。
このとき、遺言の内容に応じて公証人から必要書類を求められますので、作成前に準備しておきます。
遺言公正証書の場合、公証人に支払う作成手数料は遺言者の資産の額に応じて決まりますので、おそらくこのときに資産を示す資料も求められます。
ただし、どこまで厳密に資産の資料を求めるかは、公証人によって違いがあるのが現状です。
③証人の確保
公正証書遺言を作成する際に、立ち会ってもらう証人2名を決めます。
もし、遺言者が証人を用意できない場合、その旨を申し出ると公証役場が用意してくれますが、1人あたり1万円程度の日当を支払うことになります。
④公証役場へ
公証人と公証役場に行く日程を調整し、必要書類を持参して公証役場へ行きます。
公証役場で、まず公証人に必要書類の原本を最終確認してもらいます。
⑤遺言の口授
公証人から本人確認等を受けたのち、証人2人の立ち合いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えます。
⑥公証人による証書作成と確認
公証人が遺言者から聞いた内容を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせます。
と、条文上はこのようになっているのですが(民法969条3号)、現在公正証書はほとんどパソコンで作成され印字されています。
その関係で、公証人が遺言者から聞き取った原案を、事前に用意しているのが実態になっています。
⑦遺言者と証人による確認と署名押印
遺言者及び証人が、内容の正確なことを確認し、それぞれが署名押印します。
⑧公証人による公証
公証人が、「民法969条の方法に従い真正に作成された旨」を付記し、署名押印します。
公正証書遺言の正本が遺言者に渡され、公証人の手数料を現金で支払って終了です。
ここまで、スムーズにいけば公証役場に滞在する時間は30分もありません。
3 公正証書遺言のメリット
(1)遺言の内容が法的に正確なものであり、書き間違い等もない。
専門家である公証人が関わって遺言書が作成されるので、できあがった遺言状は、その内容に法的な誤りがあるとか、書き間違いがあるとか、文言の意味が不明確ということがありません。
これは、遺言書がトラブルを防ぐために作成されるものであることを考えると、とても重要なことです。
(2)紛失や、変造のおそれがない
遺言者には公正証書の正本(謄本)が交付され、原本は公証役場で保管されます。
そのため、万が一この正本(謄本)を紛失しても、再度謄本を受け取ることが可能です。
さらに、第三者が書き換えたとしても、原本が公証役場に保管されているので、変造はすぐに明らかになります。
なお、相続開始後、相続人が公証役場に問い合わせれば、全国の公証役場のどこかに遺言が保管されていないか、確認することができます。
(3)家庭裁判所による検認が必要ない
公正証書遺言は、自筆証書遺言等のように家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。
公証役場に原本が保管されており、変造等のリスクがないので、家庭裁判所で遺言の形式を確認する必要がないからです。
4 公正証書遺言のデメリット
(1)手続きに時間と手間がかかる
自筆証書遺言は、紙とペン、印鑑があれば思い立った時にいつでも作成できます。
一方で、公正証書遺言は、準備や手続に時間と手間がややかかります。
手続は先ほど述べたとおりで、必要書類を準備する時間も必要です。
思い立ったその日に仕上がるというものではありません。
通常は数週間、どれだけ急いでも1週間は必要になるのではないでしょうか。
ですので、死期が迫ってきてから公正証書遺言を作成しようと考えていると、作成できずに亡くなる恐れもあります。
(2)費用がかかる
公正証書遺言の作成には、公正証書に記載する財産の価額に応じて公証役場所定の手数料がかかります。
手数料は以下のとおりです。
| 100万円まで | 5000円 |
| 200万円まで | 7000円 |
| 500万円まで | 11000円 |
| 1000万円まで | 17000円 |
| 3000万円まで | 23000円 |
| 5000万円まで | 29000円 |
| 1億円まで | 43000円 |
| 1億円を超え3億円まで | 5000万円毎に1万3000円 |
| 3億円を超え10億円まで | 5000万円毎に1万1000円 |
| 10億円を超える部分 | 5000万円毎に8000円 |
5 まとめ
公正証書遺言について、イメージをもっていただけたでしょうか。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較すると、手間や費用がかかります。
しかし、その分、内容が不正確で自分の意図した相続がなされないなどのトラブルが防げますし、紛失や変造という心配もなくなります。
既に述べた通り、公正証書にする前に弁護士に文案の相談をすることもできます。
公正証書遺言の作成を検討されている方は、まずお気軽に弁護士にご相談ください。
このコラムの監修者

-
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。








