
相続放棄申述期間(3か月)の期限が過ぎた場合の処理
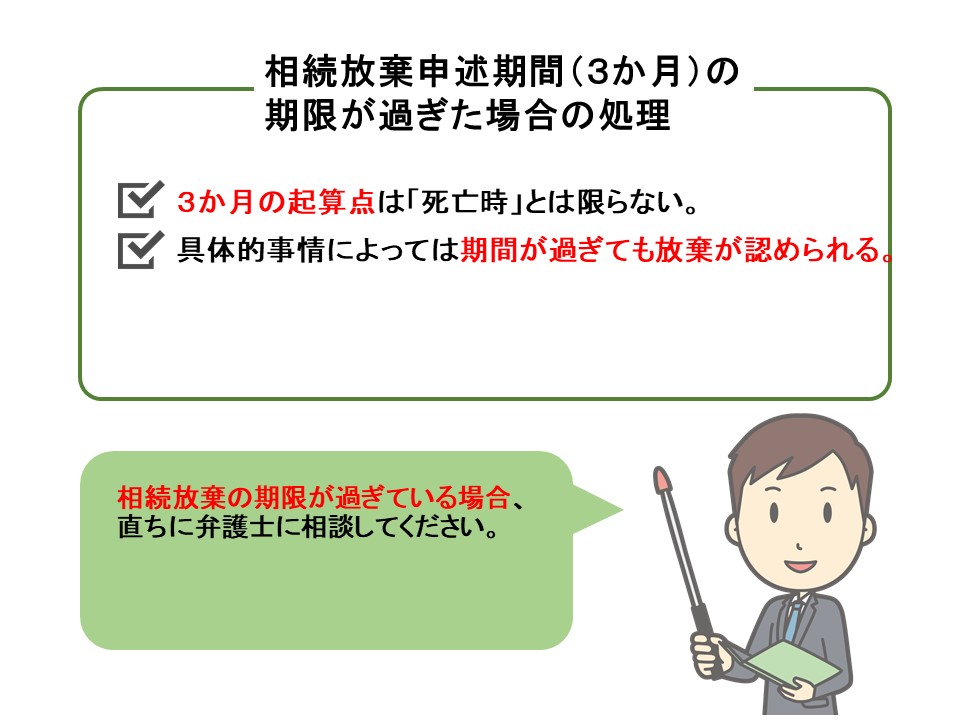
被相続人の財産や債務の相続をすべて放棄する「相続放棄」の手続きは、相続開始を知ったときから3か月以内とされています。
この3か月を過ぎてしまった場合、どのように対処すればいいのか詳しくご紹介します。
そもそも3か月の起算日はいつになるのか
相続放棄は被相続人のすべての財産を把握し、相続人が集まって遺産分割協議を行ったり、必要な書類を用意して裁判所で申述を行ったりと、何かと手続きに時間がかかります。
こうした事情を配慮して、相続放棄をするかしないかを判断するために3か月間の熟慮期間を設けているのです。
このような趣旨から、相続放棄申述期間の起算日は、「被相続人が亡くなった事実」と「被相続人と自分との身分関係を知ったとき」の両方がそろったときになっています。
被相続人である親と子どもが頻繁に会ったり、連絡を取ったりしていれば「被相続人と自分との身分関係」を知っていて当然です。
しかし、被相続人との身分関係を把握できないケースもあります。
例えば、被相続人である男性が、何十年も前に離婚した元妻との間にできた子どもなど、ずっと疎遠だった場合は、相続が開始されたことをすぐに知らされないかもしれません。
このようなケースでは、被相続人が死亡した知らせを受けた日が、相続放棄の3か月の起算日となります。
申述期間を過ぎるとどうなる?
相続人は、3か月の申述期間を過ぎると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります。
しかし、法律上「相続」は財産ばかりではなく、借り入れや連帯保証人などの債務も相続します。もしも被相続人の遺産が財産より債務が多い場合は、相続放棄をするのが一般的です。
巨額の負債を相続してしまい、相続人が返済できず自己破産するリスクも十分に考えられるため、相続放棄はできるだけ早く手続きを進めた方が賢明でしょう。
例外的に相続放棄が認められるケース
ただ、こうした厳格なルールが定められている中で、特段の事情があれば例外的に相続放棄を認める裁判例もあります。
そのほとんどが「相続財産がないと思っていたが、被相続人の死亡から3か月を過ぎた後に債務が見つかった」というケースです。
相続財産がないと信じるに値する相当の理由があれば、3ヶ月を過ぎた後も相続放棄が認められる可能性があります。
過去の判例では、次のような事案で相続放棄を認めています。
- ・「被相続人に債務はない」という、債権者からの誤った情報を信じて相続放棄を行わなかったが、実際には借金があった。
- ・被相続人死亡後、3ヶ月を経過した後に債権者から督促状が届き、多額の借金をしていることが判明した。
相続放棄申述期間を過ぎてしまったら弁護士に相談を
相続開始後、法律を知らずに相続放棄の手続きをせず債務を相続してしまったとしても、基本的に法律の不知は許されないため、相続を承認したものとみなされます。
法律の世界では「知らなかったでは済まされない」のです。
とはいえ、「債務がないと信じられるような相当な理由」さえあれば、申述期間を過ぎた後の相続放棄が認められる可能性もあります。
申述期間を過ぎたものの、どうしても相続放棄をしたい場合、相続に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄をしなかった理由が、正当であると認められ、債務を相続せずに済む可能性もあります。
このコラムの監修者

-
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。








