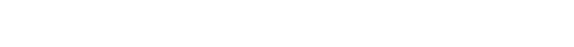
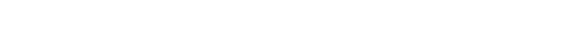
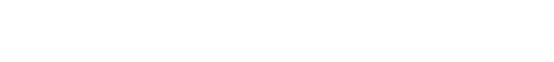


遺産分割において、亡くなった被相続人が残した財産が、預貯金よりも住宅や土地等の不動産の方が高額になるケースは珍しくありません。そのような状況で遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額を請求した時は、請求に応じなければなりません。金額の算定や評価をめぐって問題が発生することも多いです。
しかし、遺留分に相当する現金がない場合や、遺留分権利者(遺留分侵害額請求をした人)が不動産の取得を希望している場合、どのようにして解決できるでしょうか。
この記事では遺留分侵害額請求で不動産を取得する際の注意点を解説します。不動産の評価額の計算方法、調停の流れ、相続時の法定相続分との関係を紹介します。この記事を読めば、遺産評価の基礎知識から実際の対処法まで理解できるでしょう。
遺産が不動産だけの場合でも遺留分侵害額請求は可能です。
目次
遺留分とは、民法で保障された相続人の最低限の取り分のことです。法定相続分を基礎に割合が定められています。被相続人は原則として自分の財産を自由に処分できますが、一定の相続人には最低限の相続分を確保する権利があります。この制度を遺留分制度といいます。
遺留分が認められるのは、配偶者、子ども、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言書で「全財産を長男に相続させる」と書かれていても、他の相続人は遺留分侵害額請求が可能です。自分の遺留分に相当する金銭を請求できます。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の3分の1、それ以外のケースでは遺産の2分の1です。
遺留分の権利により、残された家族の生活保障が図られています。特に遺産に不動産が含まれる場合、評価額や時価の捉え方によって受け取れる金額が変わるため注意が必要です。
遺留分侵害額請求では、遺留分請求者は返還を求める財産を決められないのに対し、遺留分侵害者は不動産または金銭か、譲渡する財産を選ぶことができます。
例えば、遺留分請求者が「お金はいらないから不動産がほしい」と、現物での返還を求めていても、遺留分侵害者が「不動産は渡せないが、遺留分相当額の金銭なら渡せる」と主張することができるのです。これは評価額に基づき金銭で弁償する「価額弁償の抗弁」です。ただし不動産は時価が変動しやすく、計算方法を誤るとトラブルが生じやすいので注意が必要です。
ただ、基本的には「現物返還の原則」といい、相続財産の中に不動産が含まれていれば不動産を遺留分に応じて受け取ることができるとされています。
その一方で、「不動産ではなく、現金がほしい」と主張するケースも考えられます。もしも手元に遺留分相当額の現金がない場合は、どのように処理すれば良いでしょうか。
例えば、AとBで5000万円の不動産と500万円の預貯金を分割するところを、「不動産はすべてAに、預貯金はAとBで250万円ずつ相続させる」という遺言があった場合、AはBの遺留分を侵害していることになります。
Bは、遺留分相当額にある5000万円×1/4=1250万円を遺留分減殺請求できますが、Aに1250万円の現金がなければ、不動産を共有名義にした後に①持分移転登記をするか②売却後に代金を取得するか、いずれかの方法があります。
遺留分侵害額請求で不動産を取得した場合、当該不動産は遺留分請求者と遺留分侵害者と共有名義になります。これを単独名義にするには持分移転登記を行います。
遺留分請求者と遺留分侵害者が、共有名義不動産の売却について同意している場合は、共同で売却手続きを行います。これは、遺留分侵害者が単独で不動産を売却し、遺留分権利者に実際の売却代金よりも低く申告する可能性があるためです。そして、売却代金から諸経費を差し引いた遺留分相当額を取得します。
いずれの手続きも遺産分割時に評価基準を明確にしておくことが重要です。
遺産が不動産の場合に用いられる評価方法として以下が挙げられます。
それぞれの基準や算定根拠を理解することが必要です。
国税庁が毎年公表する相続税路線価を使って評価する方法です。路線価は道路に面した土地1平方メートル当たりの価格を示しており、無料で確認できるため手軽に概算できます。
ただし路線価は時価の約8割程度に設定されているため、手軽で無料ですが時価より2割ほど低く算出される傾向があります。そのため遺留分を請求する側は、不動産評価額の高い方が請求できる金額も増えるため、路線価での計算は不利なケースが多いです。
相続税路線価は簡易的な評価方法として理解しておきましょう。正確な評価が必要な場合は、他の方法と組み合わせて検討することをおすすめします。
市区町村が毎年送付する固定資産税課税明細書に記載された評価額を用いる方法です。課税明細書は毎年5月頃に届くため、手元の書類で簡単に確認できます。費用もかからず手軽な評価方法です。しかし固定資産税評価額は時価の約7割程度に設定されているため、実際の市場価格よりかなり低くなります。
遺留分を請求する立場では、評価額が低いと受け取れる金額も少なくなってしまいます。固定資産税評価額だけで判断するのではなく、他の評価方法も検討することが大切です。簡易的な目安として活用しましょう。調停や訴訟時には補助資料として扱われます。
国土交通省が公表する地価公示や都道府県が調査する基準地価を参考にする方法です。対象となる不動産の近くにある標準地や基準地の価格データを基に、評価額を算出します。費用をかけずに調べられる点がメリットといえるでしょう。
ただし地方エリアでは近隣に参考となる地点が少ないケースがあり、適切なデータが見つからない場合は評価が難しくなります。対象不動産と標準地の条件に違いがある場合、正確な評価ができないこともあります。
都市部で類似する地点が多い場合に有効な方法です。概算として活用し、必要に応じて他の評価方法と併用しましょう。
不動産鑑定評価は不動産鑑定士に依頼して、時価を正式に算出する方法です。費用は発生しますが、最も精度の高い時価を算出できる点が大きなメリットといえます。
評価額が数千万円程度の不動産であれば、鑑定料は30万円から40万円程度が目安です。評価の難しい土地・家屋では、鑑定料が高くなる場合もあります。
相続人で評価額の合意が難しい場合や、訴訟に発展する可能性がある場合は、客観的な証拠として不動産鑑定評価書が有効です。費用はかかりますが、確実性を重視する人に向いている評価方法です。
相続人の間で不動産の評価額について合意できない場合は、家庭裁判所の調停を経て解決を図ります。双方が出した評価額の中間値を基準に算定し、金額を確認することが多いです。遺留分に関する紛争では、調停前置主義が採用されているため、訴訟を起こす前に家庭裁判所で調停を申し立てる必要があります。
調停では、双方が主張する評価額の中間値で合意を目指すケースが一般的です。折り合いがつかない場合は、裁判所が不動産鑑定士を選任し、専門的な鑑定評価を依頼することもあります。最終的には裁判所が不動産の適正な評価額を認定し、遺留分の金額を確定させます。
ただし裁判手続きに進んだとしても、必ずしも自分に有利な結果になるとは限りません。裁判に進む前に弁護士に相談し、見通しを確認しておきましょう。
持分移転登記も不動産の売却代金の取得も、遺留分権利者と遺留分侵害者との話し合いが進まなければ解決は難しくなります。また、手続きそのものも煩雑で難しいと感じるものです。
不動産の評価や登記変更には専門知識が必要です。調停の段階から専門家に依頼することで、不要な問題を防ぎ、適正な評価額に基づいた公平な解決が可能です。
遺留分侵害額請求で不動産を取得する場合、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。相続に詳しい弁護士が、詳しくお話をうかがいスムーズな解決を図ります。
このコラムの監修者

福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。
親が亡くなってしまった時には遺言書を確認し、遺産分割を進めていきます。 しかし、中には遺言書で不公平な遺産分割を指示されており、納得ができないという方も多いでしょう。 こういった場合、遺言書で多くの遺産を譲り受けた人から他の法定相続人は遺留分の請求を行うことが可能です。ただし遺留分の請求は被相続人の兄弟・姉妹は対象外となります。 なぜ兄弟・姉妹...
詳しく見る遺留分とは 以下のような事例を考えます。 AとBは夫婦で、C、D2人の子どもがいました。 AとBは、定年後A名義の預貯金を取り崩しながら老後を暮らしていました。 Aは亡くなる直前、すべての預金を慈善団体に寄付してしまいました。 Aが亡くなったときには遺産は全くなく、BはA亡き後の生活資金のあてがなく困ってしまいました。 Aは、生きてい...
詳しく見る遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者もしくは子・直系尊属)に認められている、最低限の遺産の取り分です。 この遺留分は、放棄することも可能です。 では、被相続人がまだ生きている段階から、遺留分の放棄は可能なのでしょうか。今回は、遺留分放棄の具体的な手続きや注意点などを解説します。 生前でも遺留分放棄は可能 遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人につい...
詳しく見る生前贈与は、親が生前のうちに財産を特定の人へ贈与する制度であり、相続対策や子どもへの援助として広く利用されています。しかし現実には、「生前贈与は兄弟にばれるのではないか」「後から相続トラブルに発展しないか」といった不安を抱える人が少なくありません。 本記事では、生前贈与が兄弟に発覚する理由や確認方法、生前贈与が原因で起こりやすい相続トラブル、特別受益・遺留...
詳しく見る